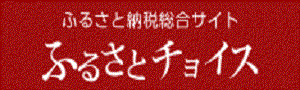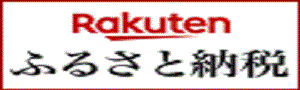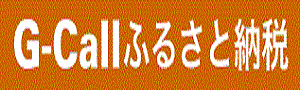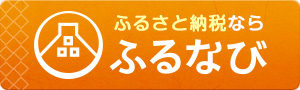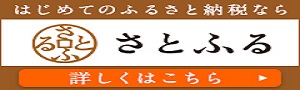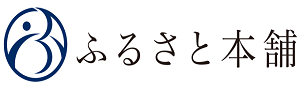本文
ふるさと納税
ふるさと納税とは、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体に寄附をした場合に、個人住民税及び所得税を一定限度まで控除する仕組みです。
この制度は、納税者個人が生まれ育ったふるさとに貢献したい、あるいは自分とかかわりの深い地域を応援したいという思いを実現する観点から、寄附という手続きを通じ、納税者が自らの意志で納税(寄附)先の自治体を選択できるものです。
ふるさと納税の使い道
主要な施策・事業等の費用の一部に寄附金を活用します
- 地域づくりに関する事業
- ケーブルテレビ番組の充実
- 地域づくり推進事業基金に積立 等
- 基盤づくりに関する事業
- 町営バスの車両更新や増便
- 公共施設等整備基金に積立 等
- 生活環境づくりに関する事業
- ごみステーションの整備、運営
- 地区公園、都市公園の整備
- 体育施設管理運営基金に積立 等
- 学習環境づくりに関する事業
- 老朽小学校の改築、耐震化、大規模改修
- 中学生海外交流派遣の充実
- 人材育成基金に積立 等
- 安全で安心な暮らしづくりに関する事業
- 防災行政無線の保守、備蓄品の購入
- 環境整備基金に積立 等
- 社会福祉の充実と健康づくりに関する事業
- 老朽保育園の改築、耐震化
- 学童保育施設の整備
- 健康福祉基金に積立 等
- 産業づくり、消費生活と雇用環境づくりに関する事業
- 農業生産基盤整備
- 企業誘致活動の充実
- 宿泊研修施設管理運営基金に積立 等
関連ファイル
ふるさと納税の方法
津幡町では次の方法でふるさと納税を受け付けています。
クリックするとページにとびます。
また、ふるさと納税ポータルサイトを利用せず役場へ直接申込も受け付けております。
津幡町電子申請サービス<外部リンク>のほか郵送やFaxで申込いただけます。郵送・Faxをご利用の場合は下記関連ファイルから申請書をダウンロードし、お送りください。
送付先
〒929-0393
石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
津幡町役場 産業建設部 商工観光課 ふるさと納税担当 宛
Tel:076-288-6120 Fax:076-288-6470
ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください!
ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。津幡町への寄附は上記の方法をご利用ください。
関連ページ:ふるさと納税の偽サイトに気を付けましょう!(消費者庁)<外部リンク>
関連ファイル
ふるさと納税による税金の控除について
ふるさと納税をした場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税の還付と住民税の控除を受けることができます。
計算方法
- 所得税(所得控除)の軽減額
A (寄附金の合計額-2,000円)×所得税の税率
※控除対象となる寄附金の上限額は、総所得金額等の40%になります。
※令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。 - 住民税(税額控除)の軽減額【B+C】
B 基本分(寄附金の合計額-2,000円)×10%
※控除対象となる寄附金の上限額は、総所得金額等の30%になります。
C 特例分(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
※Cの金額については、住民税所得割額の20%が上限となります。
※総務省のウェブサイトで寄附金控除額の計算シミュレーションが出来ます。
関連サイト:ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」(総務省)<外部リンク>
ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告を行わない給与所得者等の方は、個人住民税課税市町村に対するふるさと納税(寄附)の控除申請を寄附先の団体が本人に代わって行うことで、寄附金控除を受けられる制度が平成27年4月1日より開始されました。
この制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、翌年度の個人住民税から控除を受けることになります。この場合、確定申告は不要となります。
対象者
確定申告や住民税の申告を行う必要がない方で、その年にふるさと納税(寄附)を行う団体の数が5以下であると見込まれる方。
申告特例の申請
寄附をする際に、寄附先団体(津幡町)に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出し、申請手続きを行います。
ただし、住所変更などにより、申告特例書に変更があった場合には、寄附をした翌年の1月10日までに寄附先団体(津幡町)へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
ただし、5団体を超える自治体にふるさと納税(寄附)をした方やふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行った方は、これまでどおり確定申告書への記載が必要になります。
住民税の寄附金控除に関する問合先
住民税の寄附金控除に関して不明な点がありましたら、税務課までお問い合わせください。
津幡町役場 町民生活部税務課
住所 〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
Tel 076-288-2123 Fax 076-288-7935
メール zeimu@town.tsubata.lg.jp
ふるさと納税返礼品の募集について
ふるさと納税制度を通じて、津幡町の魅力を広く発信するために、返礼品を提供いただける事業者を募集します。
詳しくは関連リンクをご覧ください。